イデオロギー
この記事の内容の信頼性について検証が求められています。 確認のための文献や情報源をご存じの方はご提示ください。出典を明記し、記事の信頼性を高めるためにご協力をお願いします。議論はノートを参照してください。(2014年4月) |
| 社会学 |
|---|
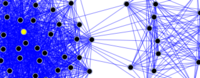 |
一般的な側面 |
社会学史 - 実証主義 領域: 小児 - 文化 |
関連分野および隣接分野 |
カルチュラル・スタディーズ 社会言語学 - 社会福祉学 |
| 政治 |
|---|
政治関連
|
サブカテゴリ
|
Portal:政治学 |
イデオロギー(独: Ideologie, 英: ideology)とは、観念の体系である。文脈によりその意味するところは異なり、主に以下のような意味で使用される。観念形態、思想形態とも呼ばれる。意味内容の詳細については定義と特徴の項目を参照。
通常は、政治や宗教における観念を指しており、政治的意味や宗教的意味が含まれている。
世界観のような、物事に対する包括的な観念。- 日常生活における、哲学的根拠。ただ日常的な文脈で用いる場合、「イデオロギー的である」という定義はある事柄への認識に対して事実を歪めるような虚偽あるいは欺瞞を含んでいるとほのめかすこともあり、マイナスの評価を含むこともある。
- 主に社会科学の用法として、社会に支配的な集団によって提示される観念。殊にマルクス主義においては、階級的な立場に基づいた物の見方・考え方。
目次
1 歴史
2 定義と特徴
2.1 マルクス主義による定義
2.2 科学技術とイデオロギーの関係
3 日本におけるイデオロギー研究
4 現代への課題
4.1 マルクス主義的な見方の限界
4.2 構造主義によるイデオロギー終焉論
4.3 経済学におけるイデオロギー終焉論
4.4 多元主義的立場からのイデオロギー終焉論
5 年譜
6 脚注
7 参考文献
7.1 上記参考文献以外のイデオロギーを扱った文献
7.1.1 日本語に翻訳されているもの
7.1.2 海外の文献
8 関連項目
歴史

デステュット・ド・トラシー
イデオロギーという用語は初め、観念の起源が先天的なものか後天的なものかを中心的な問題とする学の名であった。この用法はデステュット・ド・トラシー(Destutt de Tracy)『イデオロジー原論』(1804-1815)に見られる。
彼に代表される活動家達はイデオローグ(idéologue)と呼ばれ、1789年のフランス大革命以降、怪しげなものとして見られていたアンシャン・レジーム時代の思想のなかで啓蒙主義的な自由主義を復興させようとし、革命期から帝政にかけてフランスリベラル学派の創始者、指導的立場となった。
当初は人間の観念に関する科学的な研究方法を指していたが、やがてその対象となる観念の体系そのものをいうようになった。
定義と特徴
イデオロギーの定義は曖昧で、また歴史上その定義は一様でない。イデオロギーの定義には認識論を含むもの、社会学的なものがあり、互いに矛盾している。しかし、それぞれが有意義な意味を多数もっている。そのためディスクールや同一化思考などの類似概念と置き換え可能ではない。以下イデオロギーの定義の重要な意味内容について、主に認識論や社会学的成果をもとに解説する。

大正デモクラシーの政治的イデオロギーともいえる天皇機関説を述べた美濃部達吉
イデオロギーは世界観である。しかしイデオロギーは開かれた世界観であり、対立的な世界観の一部を取り込んでいることがある。イデオロギーは何らかの政治的主張を含み、社会的な利害に動機づけられており、特定の社会集団や社会階級に固有の観念である。にも関わらずイデオロギーは主張を正当化するために自己をしばしば普遍化したりする。またほかのイデオロギーに迎合したり、それを従属させたりする。イデオロギーは極めて政治的である。
- 同時にイデオロギーは偏った考え方であり、何らかの先入観を含む。イデオロギー的な見方をしている人は何らかの事実を歪曲して見ており、その主張には虚偽や欺瞞を含んでいることがある。イデオロギーは非合理的な信念を含んでいるが、巧妙にそれを隠蔽していることが多い。また事実関係や社会状況の一部を偽り、自己に都合のいいように改変していることがある。
イデオロギーは闘争的な観念である。イデオロギーは何らかの立場を社会において主張、拡大しようとする。また実際ある政治理念が違う立場に立つ政治理念を批判する場合、相手の政治理念が「イデオロギー的である」と指摘することがおこなわれる。イデオロギーはその意味においても何らかの価値観対立を前提としている。またあるひとがある種の政治理念を「イデオロギー」として定義している場合、そのひとはその政治理念とは異なった立場に立っていることが多い。- ある政治理念がイデオロギーであるかそうでないかは多くの場合、理念の内容それ自体よりもその理念が拡大しようとしている立場やその理念の社会状況に対する評価の仕方によって判断される。大抵の政治理念はイデオロギーになりうる。またある政治理念に「イデオロギー的である」という評価を加えた場合、それはその政治理念がある種の問題解決において本質を誤った見方をしていることを示す。
日本において戦前はリベラルな思想とされ、リベラリストから支持されていた天皇機関説は、戦後天皇主権を認めるその立場が同じリベラリストの側から保守主義を擁護するイデオロギーであると批判された。戦前は天皇主権であることは当たり前であったから、国体論や軍国主義といったイデオロギーに対抗する上で天皇機関説は正当でリベラルな思考様式であるとされたが、戦後天皇主権が自明のものでなくなったとき、天皇主権を前提とする天皇機関説によって天皇制を擁護することはイデオロギー的行為とされたのである。
以上のことから、イデオロギーは表面上中立的な政治理念を装っていることがあるが、実際は政治理念それ自体とは別個に隠蔽された政治目的を持っていることがある。イデオロギーは政治理念と政治目的が何らかの形において結合したものということができる。中立的な政治理念とイデオロギーはこの限りにおいて明確に区別される。また何がイデオロギーか何がイデオロギーでないかは立場や時代状況により一定ではない。
マルクス主義による定義

階級闘争とイデオロギー研究を結びつけたマルクス
以下はイデオロギーの定義で代表的なものと考えられるマルクスの定義をあげる。
マルクス主義におけるイデオロギーとは、観念そのものではなく、生産様式などの社会的な下部構造との関係性においてとらえられる上部構造としての観念を意味している。マルクスは最初、ヘーゲルとその後継者たちによって示された観念の諸形態について、社会的な基盤から発しながらあたかも普遍的な正当性を持つかのようにふるまう、と批判したことからイデオロギーの階級性について論じるようになる。
マルクス=エンゲルス共著『ドイツ・イデオロギー』(1845年)においてはじめてイデオロギーという用語が登場し、階級社会におけるイデオロギーの党派性が分析された。すなわち、階級社会では特定の階級が利益を得るための特定のイデオロギーが優勢になり、上部構造と下部構造の相互作用が生じて、必然的に自らを正当化するというのである。マルクスはイデオロギーのこのような性質を虚偽意識としてのイデオロギーと呼び、階級的な利害に基づいて支配体制を強化するものであると考えた。
この分析に従えば、階級制度は必ずイデオロギーを伴うものであるから、イデオロギーを批判することは階級闘争の中で最も重要な活動である。
科学技術とイデオロギーの関係

イデオロギーを含む政治行為が科学技術の目的合理性にしたがうと述べたハーバーマス
ユルゲン・ハーバーマスは、現代社会では科学技術が個人の思想とは関係なく客観的に体系化されており、目的合理性において科学技術の体系は絶対的な根拠を持っているとした。ゆえにあらゆる政治行為の価値はまず目的合理性において科学的あるいは技術的に正当なものであるかどうかの判断抜きには成立せず、イデオロギーが何らかの制度を社会に確立するときに目的合理性に合致しているかどうかということは大きな影響を持つとされた。ときにはこのような目的合理性がそれ自体で支配的な観念となり、人間疎外をもたらすと指摘した。すなわちこのような目的合理性が支配的な社会では、文化的な人間性は否定され、人間行動は目的合理性に適合的なように物象化されていくと警告したのである。これは後述のシュミットに通じる考え方である。
しかし一方でトーマス・クーンのパラダイム理論が示唆するように、歴史的には科学理論も技術的に十分検証可能でないときは、必ずしも目的合理的でない、思想的な理論信仰によって主流な科学理論 —したがって科学の方向性も— が決定されてきたということが指摘されている。
このような見方に従えば、歴史的には科学とイデオロギー(と呼びうるような思想信条)の間に相補的関係が成り立ってきたということもできる。たとえば天動説はキリスト教信仰と密接に結びついていたし、地動説についても太陽崇拝であるヘルメース信仰との関連性を指摘する説がある。技術的な進歩によって地動説の正しさが裏付けられたが、技術的に完全な検証が不可能な段階では、どちらの説をとるかは思想信条によって判断されたという見方である。実際にダーウィンの進化論を否定して、聖書的な創造論を学校で教えるべきという運動がアメリカ合衆国で広汎に存在するが、これは進化論が技術的には必ずしも完全に検証されているわけでなく、—たとえばパウル・カンメラーによるサンショウウオやサンバガエル、ユウレイボヤの実験[1]のような--現在のダーウィン的な進化論で説明がつかないとされる実験結果が報告されていたり、宇宙物理学や心理学の立場からダーウィン的な進化論と対立するような目的論的な見解 —サイバネティクスによるコンプトン効果の説明[2]や心理学的な目的論など--が提示されていることによる。もちろんこれらの事実はダーウィンの進化論に懐疑を促す事実であっても、創造論を積極的に支持するような内容ではない。とはいえ、科学理論に対して技術的に検証不可能である場合、思想信条により科学理論が選択されうることは多くの科学史家が認めるところである。
したがってあらゆるイデオロギーが科学技術のような、客観的な目的合理性の上に成り立っているならば、その次元での正当性を論じることによってイデオロギー的政治行為と正しい政治行為の間に判別が可能であると考えられる。目的合理性において明らかに欺瞞を含む政治行為が、正当な政治行為であるわけはないから、社会的なコミュニケーションのレベルでのイデオロギーの摘出には十分効果を期待できる分析であるといえる。
しかしハーバーマスも指摘しているように[要出典]、このような見方の欠点は、イデオロギーが目的合理性に則った社会的なコミュニケーションの場のみで成り立っているかという点に盲目なことである。上述したように、イデオロギーの核心をなす信条や信仰は目的合理性とはほとんど関係ないから、イデオロギー的政治理念が目的合理性に則った政治行為を主張するということも成り立つため、このようなイデオロギーの分析にはあまり有効ではない。
また技術的発展によってイデオロギー的な観念支配から脱却できるかという問題がある。
カール・シュミットはハーバーマスが目的合理性と呼んだような、技術を中立的で、したがって中性的であると見なす考え方を技術信仰と呼んで非難している。技術信仰の立場に立つと、中立で中性的な技術の進歩により、あらゆる思想的な対立は解消されていくとされる。しかしシュミットによれば、このような技術は中立的であるがゆえに、さまざまな政治理念に武器として奉仕することができる。技術は中立的ではあるが、政治的に中性的ではない。技術は道徳的な目的に奉仕することもあるが、逆に非人道的な目的に奉仕することもできる。それゆえに技術的進歩は道徳的進歩ではない。したがって技術の進歩が政治的な対立を解消して、何らかの非政治的な解決をもたらすとは考えられないとした[要出典]。
シモーヌ・ヴェイユは技術のもたらす生産性の発展が必ずしも約束されたものではないこと、ある種の濫費形態が排除されても別の濫費形態が生じてくることを指摘している。ヴェイユは具体例としてエネルギー源をあげ、石油や石炭が枯渇した場合、代替されると予想されるエネルギー源が生産性において石油や石炭に勝っているというようなことは簡単に予想されず、社会がエネルギー的に優れた方向へ進化し続けるということを疑問視している。社会の生産力の発展が抑圧を必然的に解消する —なぜならマルクスによれば階級社会が消滅すればイデオロギー的抑圧なるものは存在しなくなるから— というマルクスの見方にも否定的である。またヴェイユは抑圧を批判しているはずのマルクス・レーニン主義が抑圧を生み出していることを指摘し、このことは抑圧がどのような政治体制のもとであれ存在していることを表しているとした。したがって社会発展がどんなに進んでも抑圧は存在し、その抑圧の根拠となるイデオロギーは常に存在することになる。ヴェイユによれば抑圧の形態に対し常に注意を払い、研究を怠らないことでイデオロギーの潜在を明らかにしていくべきだと述べている[要出典]。
日本におけるイデオロギー研究
日本におけるイデオロギー研究の先駆としては幸徳秋水の『廿世紀之怪物帝国主義』が注目される。この著作において幸徳は、当時の政府の膨張政策を愛国主義と軍国主義の産物であると分析し、おもに道徳的立場から批判している。当時の膨張主義が非合理な野性に発していること、国家生存の原因を領土の広狭であると偽っていること、挙国一致の名のもとに政治闘争を封殺していることなど、そのイデオロギー的性格を指摘している。
大正期の哲学者である左右田喜一郎は『文化価値と極限概念』のなかで当時の官僚的な政府の哲学を宗教的非合理的であると批判し、あらゆる文化価値を同等に尊重する文化主義・人格主義を主張した。すなわち日本の独自性という欺瞞を掲げ、学問・政治の自由を抑圧している藩閥政府イデオロギーに対して大正デモクラシーを擁護した。しかし同時にプロレタリア独裁を掲げる「社会民主主義」を階級主義的な「限られたる民主主義」と定義し、イデオロギー的に抑圧した(左右田のいう「社会民主主義」は社会主義一般を指すものと考えられ、今日的に言えば共産主義の語感に近い)。
戸坂潤は『日本イデオロギー論』を著し、日本におけるイデオロギー批判を初めて体系的にまとめあげた。日本の特権階級のイデオロギーを哲学的観念論にあるとし、その社会的適用を通じて復古主義的な日本主義が出現し、ファシズム的軍国主義と結びついて日本イデオロギーが形成、発展してきたとする。また自由主義思想がたやすく日本主義に転化しやすいという点を指摘し、自由主義を中間的な勢力とみる当時の風潮を偽りであるとした。彼はイデオロギーを客観的現実(すなわち下部構造)の歪曲された模写であり、独自に発展法則をもつと指摘している。
丸山眞男は『日本の思想』のなかで、日本社会においては伝統的にイデオロギー批判が理論的・政治的立場でおこなわれることがなく、現実肯定という形で既成の支配体制への追従が繰り返されてきたと述べた。この現実肯定という形である種の理論を無価値化することを丸山は「実感信仰」とよび、西洋の「理論信仰」と対置させているが、これは論理より感覚を重視するという意味での単なる感覚主義ではない。「実感信仰」は事実主義や伝統主義を含み、「理論信仰」は科学主義あるいは理論主義的な立場を念頭に置いていると考えられる。
藤田省三は『天皇制国家の支配原理』において、天皇制を支えたイデオロギーとしてヨーロッパ的な社会有機体説と東洋的な儒教政治論が矛盾しながら結合した「家族国家論」を措定した。この「家族国家」は内面的には政治・学問の分野において官僚主義的立場を徹底させ、外面的には「家」の拡大という形での膨張主義を伴うとされた。またこのような「家族国家論」は天皇制国家を家と同質に自然的なものと見なす非政治的な本質を持っており、このことによって天皇制それ自体は日本社会のあらゆる利害を中和する象徴としてイデオロギー的に祭り上げられたと説いている。
現代への課題
冷戦の終結後、イデオロギーの終焉を説く声が強まっている。社会民主的な中道・福祉政党が世界の大勢を占め、かつてのようなイデオロギーをふりかざすことなく職業的・専門的な政治家・官僚によって純粋に生活向上が図られる世界に向かっているのが現代である、という分析である。また思想の面からは主に構造主義者によってイデオロギーはディスクールに還元可能であるとされた。
しかし、これらの事実はイデオロギーの終焉を必ずしも意味しない。以下代表的なイデオロギー終焉論について簡単な内容を記すとともに、その問題点を指摘する。
マルクス主義的な見方の限界
資本主義社会はその経済論理をすべての階級に及ぼし、同化吸収的に階級社会を消滅させたと説かれた。ゆえにこのような社会では階級闘争は終結し、それに伴って深刻なイデオロギー的対立は解消したとされた。
しかしマルクスの見方には大きな欠陥がある。階級的な利害がイデオロギー的であることはもちろんであるが、イデオロギー自身は必ずしも階級的な利害を必要としない。つまりイデオロギーは何らかの階級制度や階級闘争を前提としない。前述のヴェイユの立場からも階級社会が解消されてもイデオロギー的抑圧がなお存在するであろうことはおそらく確実であると思われる。そもそも社会を階級闘争的にみる見方でさえ、社会的抑圧の形態を偽っているという意味でイデオロギー的であるといえる。
構造主義によるイデオロギー終焉論
またフーコーら構造主義の哲学では制度や権力に結びつく言語表現としてのディスクールによってイデオロギーは置き換え可能だとされた。彼らは実際生活上あらゆる言語は意識的にしろ無意識的にしろ権力や政治と結びついていない言語はないし、またあらゆる言語は政治的になりうることを主張し、そのような言語ないし言語的コミュニケーションをディスクールと名付けた。
構造主義者のディスクールに対しては定義でも記述したように、イデオロギーはただ政治的なだけではない。なんらか固有の見方、世界観を含み排他的である。意味的に中立的なディスクールとは代替不可能であり、イデオロギーはディスクールに還元できない固有の意味を持つ。
経済学におけるイデオロギー終焉論
さらに冷戦終結後、国際経済における資本主義の影響力が完全なものとなったため、意識的に資本主義の根本システムを改変することは事実上不可能なものとなっており、無条件で受け入れざるを得ないものとなっている。全ての経済・社会上の問題は資本主義的全体の一問題とされ、イデオロギーを介在させずに技術的に解決可能とされる。たとえば南北格差問題や紛争問題を経済上の利害に還元し、市場経済の範囲内でさまざまな調整をすることによって解決可能だとする見方である。この立場では資本主義的経済原理をすべての人が受け入れている以上、イデオロギー闘争のような根本的な思想対立はありえないと主張された。
しかし民族的な問題や宗教的な問題がしばしば国際紛争に発展することを見ても明らかなように、たとえ資本主義の原則を全ての人が認めたとしてもイデオロギー対立は存在しうる。イデオロギーの根本は信条や信念、あるいは党派的利害であって、経済原理や社会問題から出発してその思想を形成するのではない。
多元主義的立場からのイデオロギー終焉論

エルサレム
ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地であるこの都市は、古代の時代から民族問題、宗教問題などのイデオロギー闘争にさらされてきた。エルサレムを巡る問題はいまなお解決されていない
最後に現代のような価値の多様化を認めている時代状況においてはイデオロギーは相対的に合理化して眺めることが可能で、政治的正当性の根拠は不毛な観念論争ではなく現実生活に即した実利にあるという主張がある。現代の知識人は自己のイデオロギーを諧謔的に意識化することで偽りの信念を見抜くことができ、それが行動に結びつくことはないと説かれた。
これに対しては主に二つの観点から誤りを指摘することが出来る。まずイデオロギーは語られていることだけにあるのではなく、行動や社会状況にも含まれている。つまりイデオロギーは人々がどう考えるかという問題ではなく、現にある社会状況に刷り込まれ事実関係を偽っていることがあり、イデオロギー的信条を実際は信奉していないのにもかかわらず、イデオロギーに奉仕していることがある。たとえばある種のイデオロギーを掲げた政策にそのイデオロギー性を認識しつつも実利を優先して迎合することはイデオロギー的目的に奉仕していることであり、イデオロギーから自由になっているとは言えない。また実利を最優先するこのような考え方それ自体がイデオロギー的である。実利や観念、社会状況、経済原理などはそれぞれ別次元の問題である。たとえばイデオロギーの含む世界観、倫理観は現実生活の実利とは関係ない場合が多いし、実利を優先するかそれとも他の何らかの観念を優先するかは個人のイデオロギー的な問題である。イデオロギーが価値の多様化の中でほかの何らかの価値の間に埋没するという主張は正しい見方ではないといえる。
現代の国際情勢を鑑みても民族紛争などが激化しており、戦争や紛争の問題点を明らかにするためにイデオロギー的背景を明らかにすることは有意義であると考えられる。現代社会のイデオロギーはより複雑で感知しがたいものとなっていると考えられているため、時代に即したイデオロギー分析が必要とされている。
年譜
1801年 - デステュット・ド・トラシー『観念学要理大綱』
1841年 - ルートヴィヒ・フォイエルバッハ『キリスト教の本質』
1844年 - カール・マルクス『経済学・哲学草稿』
1846年 - カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス『ドイツ・イデオロギー』
1867年 - カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス『資本論』
1895年 - エミール・デュルケム『社会学的方法の規準』
1916年 - ヴィルフレッド・パレート『社会学大綱』
1922年 - ジェルジ・ルカーチ『歴史と階級意識』
1929年 - カール・マンハイム『イデオロギーとユートピア』、V・N・ヴォロシノフ『マルクス主義と言語哲学』
1947年 - テオドール・アドルノ、マックス・ホルクハイマー『啓蒙の弁証法』
1975年 - ミシェル・ペシュ『言語、意味論、イデオロギー』
1979年 - ピエール・ブルデュー『ディスタンクシオン』
脚注
^ カンメラーの実験についてはアーサー・ケストラーの『サンバガエルの謎』による。しかし、実験結果を捏造であるとする見方も根強い。
^ コリン・ウィルソンの『オカルト』によると、1969年ロンドンのインペリアル・カレッジで開かれた国際サイバネティクス会議において、デイヴィッド・フォスターが物理学的発見の哲学的意味について講演した中でコンプトン効果に言及したという。
参考文献
出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2014年4月) |
テリー・イーグルトン著、大橋洋一訳『イデオロギーとは何か』平凡社ライブラリー、1999年、ISBN 4582762816
長尾龍一著『争う神々』信山社叢書、1998年、ISBN 4797251018
藤田省三著『天皇制国家の支配原理』未來社、1966年
カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス著、古在由重訳『ドイツ・イデオロギー』岩波文庫、1956年
戸坂潤著『日本イデオロギー論』岩波文庫、1977年- 『岩波講座 開発と文化4 開発と民族問題』岩波書店、1998年、ISBN 4000108670
丸山眞男著『日本の思想』岩波新書、1961年
ディルタイ著、山本英一訳『世界観の研究』岩波文庫、1935年、ISBN 4003363728
- 古在由重著「上部構造としてのイデオロギー」(『古在由重著作集第二巻』所収)、1970年
ユルゲン・ハーバーマス著、長谷川宏訳『イデオロギーとしての技術と科学』平凡社ライブラリー、2000年
シモーヌ・ヴェイユ著、冨原眞弓訳『自由と社会的抑圧』岩波文庫、2005年
カール・シュミット著、田中浩、原田武雄訳『合法性と正当性 付「中性化と非政治化の時代」』未來社、1983年
アーサー・ケストラー著、石田敏子訳『サンバガエルの謎』岩波現代文庫、2002年
コリン・ウィルソン著、中村保男訳『オカルト 上下』河出文庫、1995年
上記参考文献以外のイデオロギーを扱った文献
日本語に翻訳されているもの
カール・マンハイム著、高橋徹・徳永恂訳「イデオロギーとユートピア」(高橋徹編『世界の名著68 マンハイム、オルテガ』所収)中公バックス、1979年
ダニエル・ベル著、岡田直之訳『イデオロギーの終焉』東京創元社、1969年
ジェルジ・ルカーチ著、城塚登ら訳『歴史と階級意識』白水社、1987年- アドルノ、ホルクハイマー著、徳永恂訳『啓蒙の弁証法』岩波書店、1990年
- パウル・ド・マン著、大河内昌ら訳『理論への抵抗』国文社、1992年
フリードリヒ・ニーチェ著、原裕訳『権力への意志』ちくま学芸文庫、1993年
ルイ・アルチュセール著、西川長夫、伊吹浩一、大中一彌、今野晃、山家歩訳 『再生産について』、2005年
海外の文献
- マーティン・セリガー『イデオロギーと政治』(Martin Seliger,Ideology and Politics,1977)
関連項目
- 政治哲学
- 観念論
- 宗教
- マルクス主義関係の記事一覧
- ディスクール
イドラ (ラテン語: idola、ラテン語イドルムidolumの複数形)- カール・マルクス
- カール・マンハイム
- テリー・イーグルトン
- ユルゲン・ハーバーマス